【記事内に広告が含まれる場合があります】
最近Move To Earn系のプロジェクトの勢いが止まらないですよね。
そんな中で登場したのが『Fitmint』です。
注目度は第2のSTEPNとも言われるほど。
今回はそんなFitmintの特徴や始め方などをまとめていきます。
Fitmintとは?
Fitmint(フィットミント)とは、インド発のMove & Earnプロジェクトです。
歩いたり、走ったり、運動したりすることで、仮想通貨やNFTが手に入ります。
ウォーキングやランニングだけではなく、筋トレやワークアウトで報酬がもらえるのが、他のMove To Earn系アプリと違う特徴ですね。
ただ歩くだけではなく、ジムに行ってトレーニングする方にも向いているかもしれないですね。
スニーカーの種類
Fitmintで使われるスニーカーの特徴をまとめていきます。
タイプ
Fitmintのスニーカーには5つのタイプがあります。
- Basic
- Athlete
- Pro-athlete
- Legend
- Special edition
タイプによって、レア度やスタータスの個体値などが変わってくる感じですね。
ステータス
Fitmintには4つのステータスがあります。
- Power:FITTトークンを獲得するレート
- Durability:耐久性
- Stamina:エネルギーのブースト頻度
- Comfort:未定(開発中)
これらの組み合わせによって、FITTトークンの稼ぎやすさが決まってくるイメージですね。
各個体値は1〜7に設定されています。
トークン
Fitmintの通貨(トークン)は『$FITT』が採用されています。
$FITTは
- ゲームプレイ(スニーカーのアップグレード・修理・ミントなど)
- ステーキング(保持することによる金利獲得)
- ガバナンス(プロジェクトの方向性を決定)
などに利用できます。
Fitmintの始め方
Fitmintは、この記事を書いている2022年4月2日時点で、正式版のアプリはリリースされていません。
クローズドβ版の募集は始まっているので、ここではβ版への参加方法を紹介します。
① ホワイトリストに申し込む
Fitmintのホワイトリストに申し込むと
- β版アプリへの招待
- スニーカーのプレゼント(抽選)
の2つを獲得できる可能性があります。
申し込みはFitmintホワイトリストのページからできます。
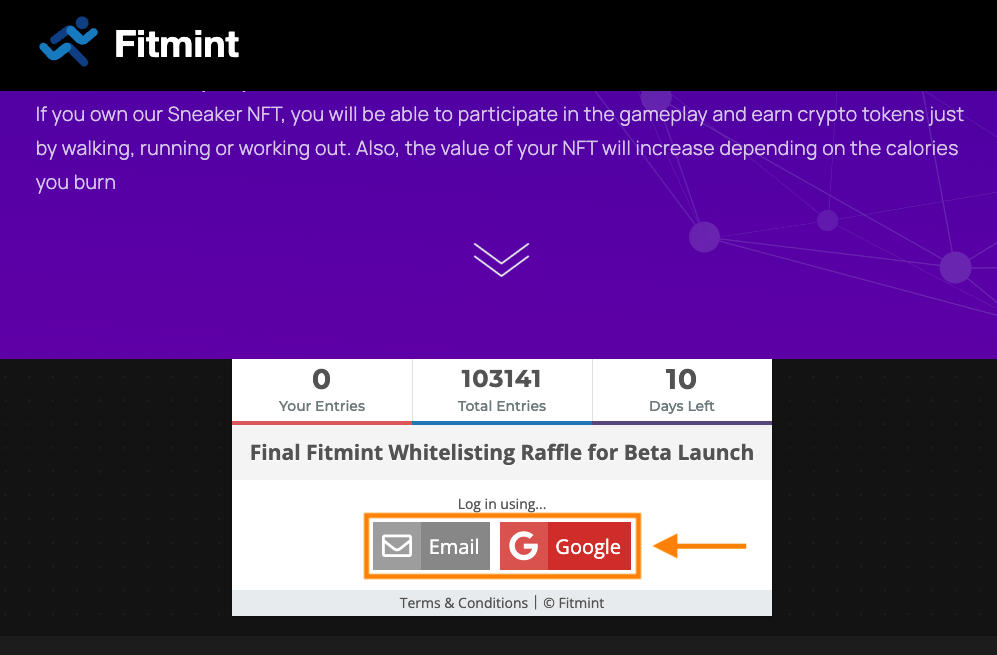
ページに進んで、下のほうにスクロールするとログイン画面が出てくるので、EmailかGoogleか好きなほうを選んでください。
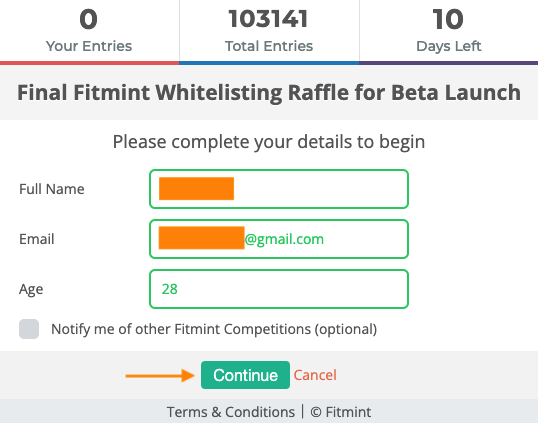
名前・メールアドレス・年齢を入力して、「Continue」ボタンを押していきましょう。
これで申し込み手続きは完了で、下の画面が出てきます↓
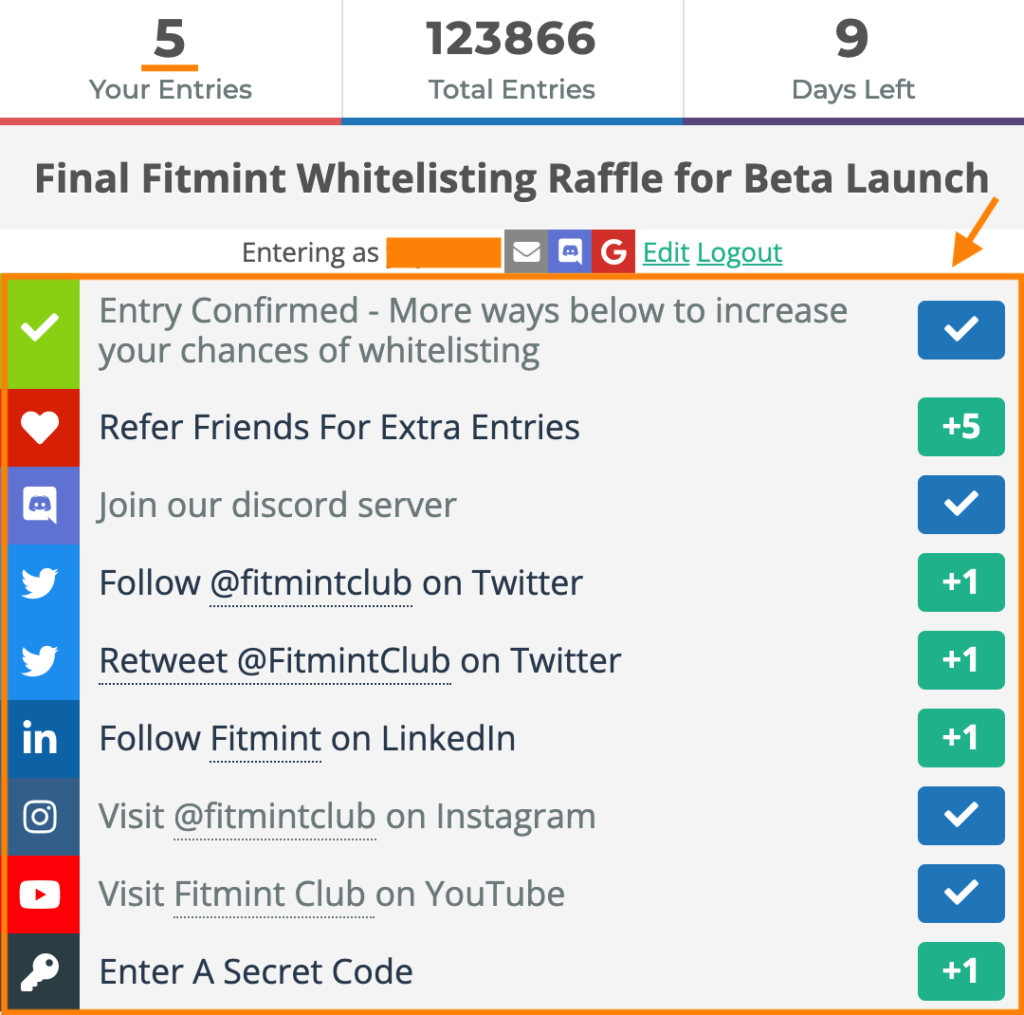
ここに載っているタスクにエントリーするほど、スニーカーの当選確率を上がります。
SNSのフォローやリツイート、Discordへの参加など色々あるので、できるものからやっていきましょう。
エントリーができると、左上の部分に数字が追加されていきます。
② アプリをインストールする
ホワイトリストに申し込むと、クローズドのβ版アプリに招待される可能性があります。
連絡が届いたらアプリをインストールしていきましょう。
クローズドβ版アプリは「2022年5月30日」からリリースされています。
アプリをインストールできたら、スニーカーをミントしていきましょう。
スニーカーのミントには仮想通貨のMATICが必要になるので、準備しておきましょう。
MATICの買い方はこちらの記事↓にまとめています。
 仮想通貨MATICの買い方【3ステップでわかりやすく解説】
仮想通貨MATICの買い方【3ステップでわかりやすく解説】 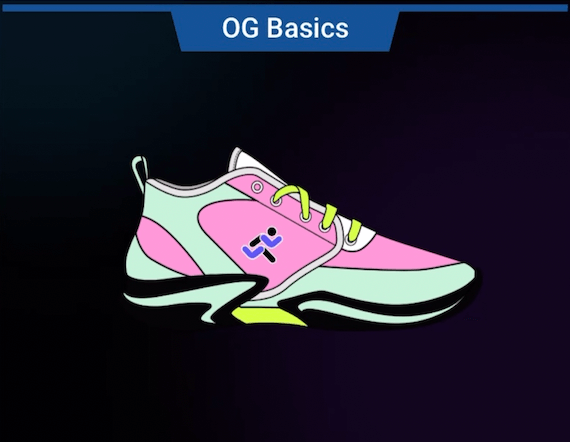
ミントできるとこんなスニーカーが手に入ります。
③ 運動を開始する
アプリをインストールしてスニーカーをミントできたら、運動を開始していきましょう!
運動をしていくことでFITTトークンが手に入ります。
Fitmintに関するQ&A
Fitmintに関する質問をいくつかまとめました。
無料でも始められる?
Fitmintでは、スタート時にスニーカーを一つもらえるので、無料で始められます。
初期費用をかけなくてもスタートできるのはありがたいですよね。
収益性を上げたい場合や、ミントしてスニーカーを増やしたい場合は、別途購入が必要になるイメージですね。
スニーカーの値段は?
Fitmintのスニーカーの値段は
- $100〜150(約12,000〜18,000円くらい)
と言われています。
まだ販売はされていないので、今後どうなるかはわからないですが、今のところはスタートしやすい価格かなと思います。
2022年4月時点でできることは?
2022年4月2日時点で、できることはこのあたりです。
ホワイトリストに申し込むと、β版のアプリへの招待やスニーカーが抽選で当たる可能性があるので、申し込んでおくといいですね。
Discordのコミュニティには日本人の方もたくさんいるので、交流や質問をするときになどに使えます。
あとは、必要に応じてホワイトペーバーを読み込んで理解を深めていきましょう。



